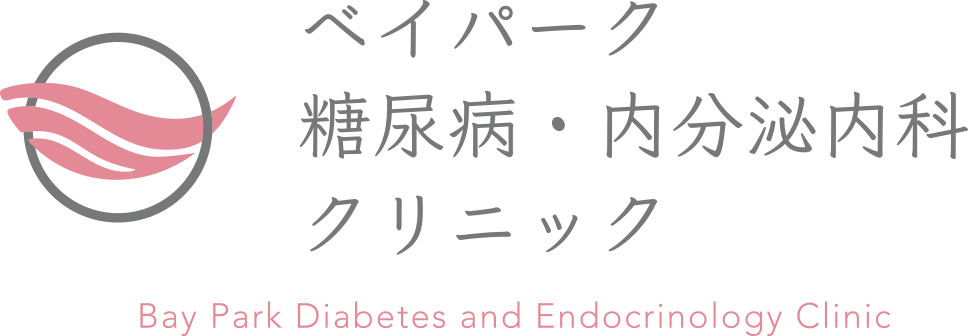このような症状の方は、
受診をお勧めします!
- ウエストのサイズが、男性で85cm以上、女性で90cm以上ある
- BMI(体格指数)が25を超えている
- お腹は出ているものの、皮下脂肪がつまめないほど少ない
- 短期間で急激に体重が増加した
- 空腹ではないのに、つい間食や過食をしてしまうことが多い
- 便秘やお腹の張りといった腹部の不快感が続いている
- むくみが気になる、または1日の排尿回数が7回未満と少ない
- 睡眠中の激しいいびき、あるいは睡眠時無呼吸症候群の疑いがある
- 糖尿病、高血圧、脂質異常症、痛風、脂肪肝などの生活習慣病を指摘されたことがある
肥満とは
 肥満とは、体内に過剰な脂肪が蓄積し、体重が基準を超えている状態を指します。肥満かどうかの判定には「BMI(Body Mass Index/体格指数)」が広く用いられ、数値が25.0以上であれば肥満とされます。さらに、BMIが35を超えると「高度肥満」に分類されます。
肥満とは、体内に過剰な脂肪が蓄積し、体重が基準を超えている状態を指します。肥満かどうかの判定には「BMI(Body Mass Index/体格指数)」が広く用いられ、数値が25.0以上であれば肥満とされます。さらに、BMIが35を超えると「高度肥満」に分類されます。
このBMIは、以下の計算式で求めることができます。
BMI (体格指数)=体重(kg)÷身長(m)2
肥満症とは
「肥満」が体内に脂肪が過剰に蓄積している状態そのものを指すのに対し、「肥満症」とは、肥満によって既に健康障害が起きている、あるいはそのリスクが高く、医学的な治療が必要とされる病的な状態を意味します。
日本肥満学会の『肥満症診療ガイドライン2022』では、以下の2つの条件をいずれも満たす場合に「肥満症」と診断されます。
- BMIが25.0以上であり、肥満と診断されていること
- 以下に示す11種類の「肥満関連疾患」のいずれかを合併していること
※これらの11疾患は、肥満が原因または関連して発症し、減量によって症状の改善が期待できると科学的に証明されているものです。
※以下の合併症が見られない場合でも、「内臓脂肪型肥満」と診断された場合には、現時点で健康障害がなくても肥満症とみなされます。
内臓脂肪型肥満は、ウエスト周囲径が男性で85cm以上、女性で90cm以上ある場合に疑われ、さらに腹部CT検査で内臓脂肪面積が100cm²以上と確認された場合に診断が確定されます。
- 耐糖能障害(2型糖尿病、耐糖能異常など)
- 高血圧
- 脂質異常症
- 高尿酸血症(痛風)
- 冠動脈疾患(心臓病)
- 脳梗塞、一過性脳虚血疾患
- 非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)
- 月経異常、女性不妊
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満低換気症候群
- 運動器疾患(膝痛、腰痛、手指関節、股関節)
- 肥満関連腎臓病
肥満症の症状
 肥満症は進行が緩やかで、初期の段階では目立った症状が現れにくいのが特徴です。しかし、体内では少しずつ異常が進行しており、次第に身体的・精神的な不調として現れてきます。
肥満症は進行が緩やかで、初期の段階では目立った症状が現れにくいのが特徴です。しかし、体内では少しずつ異常が進行しており、次第に身体的・精神的な不調として現れてきます。
まず現れやすいのが、身体の重さやだるさといった慢性的な疲労感です。階段の昇降や速歩きなど、軽度の運動で息切れを感じる場合、それは単なる体力低下ではなく、増加した体重が循環器系に過度な負担をかけているサインかもしれません。
また、内臓脂肪の蓄積により、消化機能やホルモンのバランスが崩れやすくなります。これにより、胃もたれや便秘が生じるほか、女性では月経不順や周期の乱れといった症状を引き起こすこともあります。
皮膚にも変化が現れやすく、汗をかきやすくなる、湿疹が出る、かゆみが頻発するなどのトラブルが生じる場合があります。これらは、皮脂の過剰分泌や免疫機能の低下など、肥満による代謝異常や炎症反応が影響していると考えられます。
より深刻な段階では、肥満が原因で発症する合併症の兆候が見られるようになります。高血圧による頭痛やめまい、糖尿病の進行に伴う頻尿・口渇などは、肥満症が慢性疾患へと移行し始めている明確な警告です。睡眠時無呼吸症候群によっていびきが大きくなる、眠りが浅くなる、起床時に強い倦怠感があるといった症状も、見過ごせない重要なサインです。
さらに、肥満症は精神面にも影響を及ぼします。自己肯定感の低下、抑うつ気分、不安感などが生じやすくなり、それが過食や運動の回避といった負の連鎖に繋がることもあります。
このように、肥満症は単に体重の問題に留まらず、心身の広い領域にわたって影響を及ぼす病態であることを理解することが重要です。
肥満症の原因
 肥満症は、単なる一時的な食べ過ぎや運動不足によって起こるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合い、時間をかけて進行していく病態です。なかでも中心となるのは、現代社会に根ざした不健康な生活習慣です。高カロリーかつ栄養バランスの崩れた食事、特に加工食品やファストフード、糖分の多い飲み物を日常的に飲むことで、体内に余分なエネルギーが蓄積されます。一方で、慢性的な運動不足によってそれを消費する機会が失われ、脂肪が体内に蓄えられていくという悪循環が生まれます。
肥満症は、単なる一時的な食べ過ぎや運動不足によって起こるものではなく、様々な要因が複雑に絡み合い、時間をかけて進行していく病態です。なかでも中心となるのは、現代社会に根ざした不健康な生活習慣です。高カロリーかつ栄養バランスの崩れた食事、特に加工食品やファストフード、糖分の多い飲み物を日常的に飲むことで、体内に余分なエネルギーが蓄積されます。一方で、慢性的な運動不足によってそれを消費する機会が失われ、脂肪が体内に蓄えられていくという悪循環が生まれます。
こうした生活習慣に加えて、遺伝的な体質も肥満のリスクを高める要因の1つです。親が肥満傾向にある場合、その子どもも同様の体質を受け継ぐことが多く、脂肪の蓄積しやすさや代謝機能、食欲を調整するホルモンの働きに影響を及ぼすと考えられています。ただし、遺伝はあくまで「なりやすさ」に過ぎず、必ず発症するわけではありません。
また、精神的ストレスも肥満症と深い関わりがあります。ストレスが慢性化すると、脳は快楽や安心感を求めて高脂質・高糖質の食品を欲しやすくなり、それが過食や夜食の習慣に繋がります。さらに、うつ病や不安障害といった精神疾患を抱えている場合、食欲のコントロールが難しくなり、肥満が進行しやすくなります。
加えて、睡眠不足や生活リズムの乱れも見逃せません。睡眠中に分泌されるホルモンは脂肪の代謝や食欲の調整に関与しており、慢性的な睡眠不足はこれらの機能を乱し、肥満リスクを高めます。
このように、肥満症は食生活や運動習慣だけでなく、遺伝的素因や心理状態、睡眠の質といった多面的な因子が重なり合って進行していくものであり、その予防・改善には幅広い視点からの対応が必要です。
肥満症の治療
 肥満症の治療では、体重を減らすことが第一のアプローチとなりますが、その目的は単に体重を落とすことではありません。減量によって現在生じている健康障害を改善し、将来的に発症しうる疾患を予防することが真の目的です。
肥満症の治療では、体重を減らすことが第一のアプローチとなりますが、その目的は単に体重を落とすことではありません。減量によって現在生じている健康障害を改善し、将来的に発症しうる疾患を予防することが真の目的です。
そのためには、単なる食事制限ではなく、栄養バランスを考慮しながら摂取カロリーを適切に調整する食事療法を基本とし、さらに運動療法を併用して体重の管理を図ります。
減量の目標は、通常の肥満症の場合で現体重の3%減を目安とします。例えば体重80kgの方であれば、約2.4kgの減量が初期の目標となります。BMIが35を超える高度肥満症の場合は、5〜10%の体重減少を目指す必要があります。
当院では、肥満症と診断された患者様に対して、まず管理栄養士による個別の食事指導を実施しています。こうした生活習慣の見直しによる治療でも効果が十分に得られない場合には、必要に応じて薬物療法を検討します。