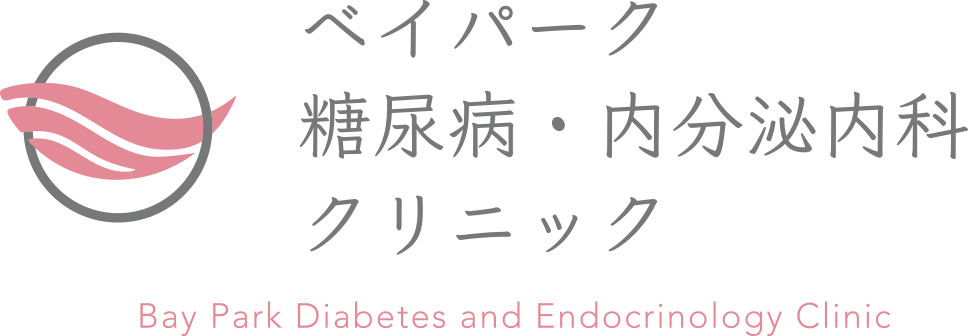血圧とは
 血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際に、血管の壁にかかる圧力のことを指します。心臓はポンプのような働きをしており、収縮と拡張を繰り返すことで血液を循環させています。
血圧とは、心臓が血液を全身に送り出す際に、血管の壁にかかる圧力のことを指します。心臓はポンプのような働きをしており、収縮と拡張を繰り返すことで血液を循環させています。
心臓が収縮して血液を勢いよく押し出すときにかかる圧力が「収縮期血圧(最高血圧)」、反対に、心臓が拡張しているときの圧力が「拡張期血圧((最低血圧)」です。
血圧の測定では、この2つの値が同時に表示され、心臓の働きや血管の状態を評価する重要な指標となります。
高血圧の定義
高血圧とは、以下のいずれかに該当する状態を指します。
- 収縮期血圧が140mmHg以上
- 拡張期血圧が90mmHg以上
どちらか一方でも基準を超えていれば「高血圧」と診断されます。
高血圧を放置すると、血管に強い負担がかかり、動脈硬化の進行や悪化に繋がります。さらに、動脈硬化が進むと高血圧をさらに悪化させるという悪循環に陥りやすくなります。いずれも自覚症状が乏しいため、気づかないうちに深刻化するケースも少なくありません。
結果として、心筋梗塞や脳卒中など、命に関わる重大な疾患のリスクも高まるため、早期発見と継続的な治療が重要です。定期的に血圧を測定し、必要に応じて医師の診察を受けることをお勧めします。
診察室血圧と家庭血圧
血圧は、体重と同様に日常生活の様々な要因、例えば運動・入浴・食事・排泄・ストレスなどによって変動しやすいです。そのため、1回だけの測定では正確な判断が難しく、複数回の測定が必要です。
血圧の種類には以下の3つがあります。
- 診察室血圧:医療機関で測定された血圧
- 家庭血圧:自宅で日常的に測定する血圧
- 24時間血圧:特殊な装置を装着し、昼夜を通じて血圧の変化を記録するもの
高血圧治療ガイドライン
日本高血圧学会が発表した『高血圧治療ガイドライン2025』にあるように、目標の数値を目指して管理していきましょう。なお、ガイドライン2019年版(ガイドライン2025年の一つ前まで)では、病気や年齢によって目標血圧値が異なっていました。今回、新たなガイドラインでは、この区別がなくなり、全年齢、病気の有無に関係なく目標血圧が統一されました。そのため、より一層患者様と医療従事者で目指すべき目標が明確になりました。
主なガイドラインについて、以下で説明いたします。
各種類の目標血圧
| 種類 | 目標血圧(全年齢統一) |
|---|---|
| 診察室血圧 | 130/80 mmHg未満 |
| 家庭血圧 | 125/75 mmHg未満 |
治療ではなく、患者様自身で血圧管理することが重要!
薬で血圧を下げるだけでなく、生活習慣の見直しや家庭での血圧測定を通して、自分の血圧を日々管理していくことが大切です。高血圧は、自覚症状がほとんどないまま血管を傷つけていく「サイレントキラー(沈黙の殺し屋)」です。脳卒中や心筋梗塞など、命に関わる病気を防ぐためにも、毎日の血圧管理がとても重要です。
家庭での血圧測定で、自身の血圧を管理
血圧管理の主役は「患者様自身」です。そのために欠かせないのが、家庭での血圧測定です。病院で測る血圧(診察室血圧)だけでは、実際の血圧を正確に把握できないことがあります。たとえば、以下があります。
| 白衣高血圧 | 病院だと緊張して血圧が高くなる |
|---|---|
| 仮面高血圧 | 病院では正常でも、家庭では高い |
上記のような隠れた高血圧を見逃さないためにも、自宅での測定がとても大切です。特に、脳卒中などのリスクと関係が深い早朝の血圧をチェックすることが重要とされています。
家庭血圧の測り方(推奨手順)
朝と夜の2回を目安に測り、1〜2週間分の記録をつけて医師に見せるようにしましょう。記録のデータが、治療や生活習慣の見直しに役立ちます。
| 朝 | 起床後1時間以内、朝食前、排尿後に測定 |
|---|---|
| 夜 | 就寝前に測定 |
高血圧の原因
 高血圧には、大きく分けて「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の2つのタイプがあります。二次性高血圧は、腎臓や内分泌系の疾患、あるいは一部の薬剤の影響など、明確な原因が存在するタイプであり、原因疾患の治療や薬剤の中止・変更によって血圧が改善されることが多くあります。
高血圧には、大きく分けて「本態性高血圧」と「二次性高血圧」の2つのタイプがあります。二次性高血圧は、腎臓や内分泌系の疾患、あるいは一部の薬剤の影響など、明確な原因が存在するタイプであり、原因疾患の治療や薬剤の中止・変更によって血圧が改善されることが多くあります。
一方、全体の約9割を占める本態性高血圧は、はっきりとした発症原因が特定できないものの、遺伝的な体質に加え、塩分や脂質の多い食事、飲酒・喫煙習慣、運動不足、肥満、さらにはストレスや過労といった様々な生活習慣や環境要因が複雑に関与していると考えられています。そのため、本態性高血圧においては、まず生活習慣の改善が治療の基本となります。具体的には、減塩や栄養バランスの取れた食事、適度な運動、禁煙・節酒、体重の管理、ストレスの軽減などが求められます。
また、高血圧の患者様には、脂質異常症や糖尿病といった他の生活習慣病を合併していることも少なくありません。これらの疾患もまた自覚症状に乏しく、進行に気づきにくいのが特徴です。そのため、血圧だけに注目するのではなく、血糖値やコレステロール値なども含めた総合的な健康管理が重要です。
健康診断などで血圧の異常を指摘された場合、特に症状がないからといって放置するのは危険です。異常を指摘された際には、必ず専門医の診察を受け、適切な治療と生活改善に取り組むようにしましょう。
高血圧の治療
 高血圧の治療では、まず血圧を適正な範囲に保つことを目指し、減塩やカロリー制限、無理のない運動習慣の導入など、生活習慣の見直しを中心とした指導を行います。改善は一度に全てを変えるのではなく、無理のないペースで段階的に進めていくことが重要です。
高血圧の治療では、まず血圧を適正な範囲に保つことを目指し、減塩やカロリー制限、無理のない運動習慣の導入など、生活習慣の見直しを中心とした指導を行います。改善は一度に全てを変えるのではなく、無理のないペースで段階的に進めていくことが重要です。
生活習慣の改善を継続してもなお血圧が高い状態が続く場合には、降圧薬の処方も検討します。ただし、薬によって数値が下がったとしても、それで安心せず、引き続き食事や運動などの生活改善を並行して行うことが、血圧を安定的にコントロールするためには不可欠です。
また、患者様の症状や健康状態によっては、初期段階から厳格な食事管理や積極的な運動療法が求められる場合もあります。当院では、1人ひとりの生活背景や体調に応じて、最適な治療方針をご提案し、無理なく継続できるサポートを行ってまいります。
生活習慣の改善
塩分制限
 日本人の食事は、炭水化物を主食とし、副菜でタンパク質や脂質を摂る構成が基本とされています。
日本人の食事は、炭水化物を主食とし、副菜でタンパク質や脂質を摂る構成が基本とされています。
しかし、食の欧米化が進む中で、調味料の使用量や加工食品の摂取が増え、塩分の摂取量も多くなりがちです。そのため、食生活の見直しにおいて、塩分制限は非常に重要なポイントとなります。減塩を実践する際に、「味が薄い」「物足りない」と感じる方も多くいらっしゃいますが、工夫次第で美味しく続けられます。
なお、1日の塩分摂取量は6g未満が推奨されています。これは「ナトリウム量」ではなく、「食塩相当量」で算出されるもので、ハム・ソーセージなどの加工食品、漬物、インスタント食品などは特に塩分が多く含まれているため注意が必要です。
現在では、多くの食品パッケージに「食塩相当量」が記載されているため、表示をしっかり確認し、減塩の目安として活用しましょう。
以下のような食事の工夫が効果的です
- 出汁をしっかり取る
- 素材本来の旨味を活かす
- グルタミン酸を豊富に含むトマトなどと、イノシン酸が豊富な肉類を組み合わせて旨味を強化する
- 香味野菜やスパイスを積極的に使い、風味で満足感を高める
体重の減量・肥満の予防
肥満の有無を判断する指標として広く使われているのが、BMI(体格指数)です。これは体重と身長から計算され、以下の式で求められます。
BMI (体格指数)=体重(kg)÷身長(m)2
最近では、多くの電子体重計が身長を入力するだけでBMIを自動計算してくれるため、日常的な健康管理にも役立ちます。
なお、世界共通の計算式ではありますが、BMIによる判定基準は国によって異なります。日本では日本肥満学会の基準に基づき、以下のように分類されています。
| BMI | 判定 |
|---|---|
| 40以上 | 肥満4度 |
| 35~40未満 | 肥満3度 |
| 30~35未満 | 肥満2度 |
| 25~30未満 | 肥満1度 |
| 18.5~25未満 | 普通体重 |
| 22 | 標準体重 |
| 18.5未満 | 低体重 |
BMIは18.5以上25未満の範囲に保つことが、生活習慣病の予防や進行防止に効果的とされています。特に、内臓脂肪型肥満だけでなく、皮下脂肪型肥満であっても、高血圧や糖尿病などのリスクが高まることが分かっています。
ただし、体重を急激に減らそうとするのは危険です。過度な減量により思わぬ不調をきたしたり、貧血や生理不順などの症状が出る場合もあります。したがって、無理のないペースで食事を調整し、適度な運動を取り入れながら、段階的に減量することが大切です。
運動については、毎日続けられる程度の軽い有酸素運動がお勧めです。特に、1日30分程度のウォーキングは、身体への負担も少なく、始めやすい運動のひとつです。体が慣れてきたら、運動時間を少しずつ増やしていくのも良いでしょう。
なお、持病をお持ちの方の中には、運動に制限が必要な場合もあります。運動を始める際は、必ず主治医と相談のうえ、無理のない範囲で取り組むようにしてください。
減酒・禁酒
 過度な飲酒は、血圧の上昇や肥満の原因となるだけでなく、長期的には多様な健康被害を引き起こす可能性があります。飲酒量の目安としては、1日の適量は日本酒で1合(約180ml)、ビールであれば500mlまでとされています。これは「1日あたりの適量」であり、仮に休肝日を1日設けたからといって、翌日に倍量を飲んでも良いというわけではありません。
過度な飲酒は、血圧の上昇や肥満の原因となるだけでなく、長期的には多様な健康被害を引き起こす可能性があります。飲酒量の目安としては、1日の適量は日本酒で1合(約180ml)、ビールであれば500mlまでとされています。これは「1日あたりの適量」であり、仮に休肝日を1日設けたからといって、翌日に倍量を飲んでも良いというわけではありません。
禁煙
喫煙は血管を収縮させる作用があるため、血圧をさらに上昇させる大きな要因となります。
たとえ食事療法や運動療法をしっかり行っていても、喫煙を続けているとこれらの治療効果が十分に発揮されにくくなるだけでなく、呼吸器疾患の悪化や心血管疾患のリスク増加にも繋がります。
薬物療法
高血圧の治療においては、必要に応じて血圧を下げる薬(降圧薬)を使用します。降圧薬には様々な種類があり、それぞれ血圧を下げる作用の仕組みが異なります。
当院では、患者様の血圧の数値や年齢、体格、性別、生活習慣、さらに併存疾患の有無などを総合的に考慮し、最適な薬剤を選択して処方しています。
当院で扱う降圧剤のタイプ
| 降圧剤のタイプ | 働き |
|---|---|
| 利尿剤 | 尿をたくさんつくることで、血液の量が減少し、血圧がさがっていきます |
| 血管拡張剤(カルシウム拮抗薬) | 血管が拡張することで血管壁が受ける圧力を下げ、血圧が下がります |
| 神経遮断剤 | 血管を緊張させる神経の働きをおさえて、血管を拡げて血圧を下げるタイプの薬剤です |
| レニン・アンジオテンシン系薬 | 血圧を上げる働きをする、レニン、アンジオテンシン、アルドステロンといったホルモンの働きを阻害して血圧をさげます |