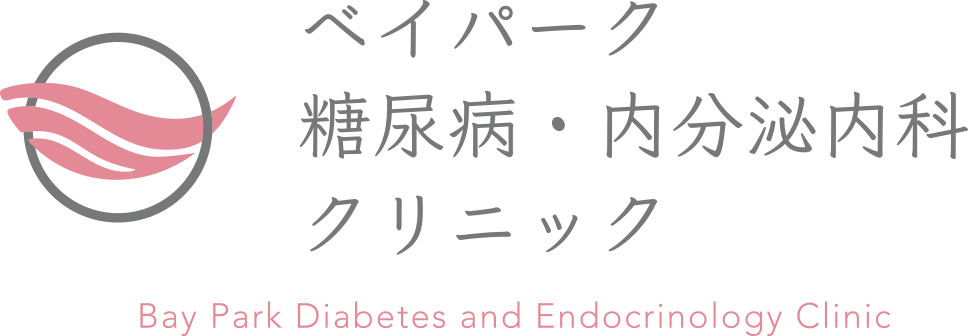高尿酸血症(痛風)とは
 高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が基準値を超えて慢性的に高い状態を指します。一般的に、尿酸値が7.0mg/dLを上回ると高尿酸血症と診断されます。尿酸が過剰になると血中では溶けきれずに結晶化し、関節や周囲の組織に蓄積して炎症を引き起こします。この激しい炎症反応が「痛風発作」と呼ばれるもので、わずかな刺激でも強烈な痛みを伴うことが特徴です。
高尿酸血症とは、血液中の尿酸値が基準値を超えて慢性的に高い状態を指します。一般的に、尿酸値が7.0mg/dLを上回ると高尿酸血症と診断されます。尿酸が過剰になると血中では溶けきれずに結晶化し、関節や周囲の組織に蓄積して炎症を引き起こします。この激しい炎症反応が「痛風発作」と呼ばれるもので、わずかな刺激でも強烈な痛みを伴うことが特徴です。
痛風発作は、尿酸値が高ければ必ず起こるわけではありませんが、高尿酸血症の状態が続くことで、尿路結石の形成リスクが高まり、さらに脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な血管障害を招く可能性もあります。
健康診断で尿酸値の異常を指摘された場合は、無症状であっても放置せず、専門の医療機関を受診し、早めに適切な対応を取ることが重要です。
高尿酸血症(痛風発作)の症状
 高尿酸血症の状態では、無症状の方も多くいらっしゃいます。しかし、痛風発作が起こると、関節に強い痛みや腫れ、発赤、熱感などの急性炎症が生じます。特に、足の親指の付け根に現れることが多いです。また、手首や肘、膝、足首など他の関節にも症状が及ぶこともあります。
高尿酸血症の状態では、無症状の方も多くいらっしゃいます。しかし、痛風発作が起こると、関節に強い痛みや腫れ、発赤、熱感などの急性炎症が生じます。特に、足の親指の付け根に現れることが多いです。また、手首や肘、膝、足首など他の関節にも症状が及ぶこともあります。
この発作は予兆なく突然始まり、発症から数時間以内に痛みのピークを迎えるのが一般的です。適切な治療を行わない場合、症状は数日から数週間にわたって続くこともあり、日常生活に大きな支障をきたします。
尿路結石も起こる?!
高尿酸血症が進行すると、尿中に排出される尿酸の量が増加し、やがて結晶化して尿路結石を形成することがあります。これらの結石は腎臓、尿管、膀胱などに生じ、尿の流れを妨げることで激しい痛みを引き起こします。
高尿酸血症(痛風)の原因
尿酸は、細胞内の核に存在する「プリン体」が分解されることで生じる老廃物です。プリン体を多く含む食品としては、エビやカニなどの甲殻類、レバーや魚の干物、魚卵、ビールをはじめとしたアルコール類などが挙げられ、これらを過剰に摂取することで、体内の尿酸値が上昇し、高尿酸血症のリスクが高まります。
また、体内の代謝異常により尿酸の産生量が増加する場合や、腎機能の低下によって尿酸の排泄がうまく行われなくなることも、高尿酸血症の原因となります。
高尿酸血症(痛風)の治療方法
痛風発作の治療
痛風発作が起きている際には、まず強い痛みと炎症を抑えることが優先されます。主に鎮痛薬や抗炎症薬を用いて、症状の緩和を図ります。
発作の最中に尿酸値を急激に下げると、症状がかえって悪化することがあるため、尿酸値の治療は発作が落ち着いてから開始します。初めて痛風を発症した場合も、同様の慎重な対応が求められます。
高尿酸血症の治療
高尿酸血症の治療は、生活習慣の改善と薬物療法を組み合わせて行います。血中尿酸値が7.0mg/dLを超えた場合は治療が必要ですが、数値を急激に下げると再び痛風発作を誘発するリスクがあるため、緩やかにコントロールしていくことが大切です。
食事療法
 高尿酸血症では、摂取カロリーの管理に加えて、プリン体の摂取制限が必要です。プリン体は多くの食品に含まれますが、特にエビ、カニ、魚卵、煮干し、鰹節、干し椎茸、干物、鶏レバー、豚肉などに多く含まれているため、これらを控えるようにしましょう。
高尿酸血症では、摂取カロリーの管理に加えて、プリン体の摂取制限が必要です。プリン体は多くの食品に含まれますが、特にエビ、カニ、魚卵、煮干し、鰹節、干し椎茸、干物、鶏レバー、豚肉などに多く含まれているため、これらを控えるようにしましょう。
また、ビールだけでなく、日本酒や焼酎などを含む酒類全般にもプリン体が含まれているため、禁酒または減酒も尿酸値の管理において重要なポイントです。
運動療法
 ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を、無理のない範囲で毎日継続することが推奨されます。
ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動を、無理のない範囲で毎日継続することが推奨されます。
他の生活習慣病や持病をお持ちの方は、運動開始前に必ず主治医と相談のうえ、身体の状態に応じた運動計画を立てましょう。
薬物療法
 生活習慣の見直しだけで効果が不十分な場合や、既に痛風発作を経験している場合には、内服薬による治療が必要となります。薬剤は、患者様の体質や病歴に合わせて処方され、目標とする尿酸値に向けて徐々に数値を下げていきます。
生活習慣の見直しだけで効果が不十分な場合や、既に痛風発作を経験している場合には、内服薬による治療が必要となります。薬剤は、患者様の体質や病歴に合わせて処方され、目標とする尿酸値に向けて徐々に数値を下げていきます。
急激な数値の変動は発作の再発を引き起こす可能性があるため、段階的に調整することが重要です。また、血中の尿酸値が正常値に達しても、体内には結晶化した尿酸が残存しているため、治療はすぐに終了せず、継続する必要があります。
自己判断で治療を中断することは避け、医師の指導のもとで根気強く治療を続けましょう。