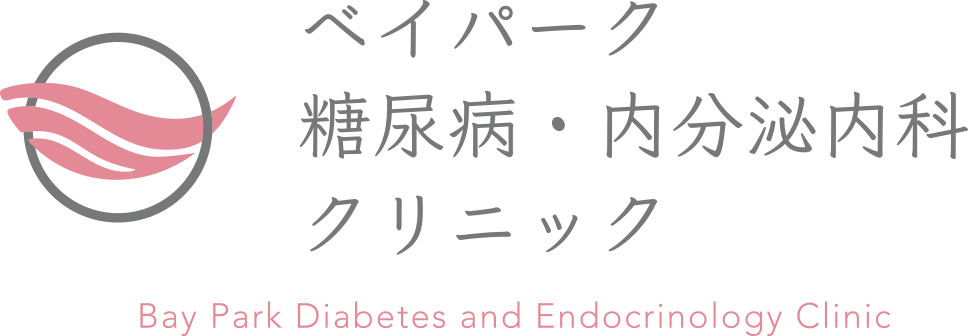糖尿病とは
糖尿病は、インスリンというホルモンが十分に分泌されなかったり、体内でうまく働かなくなったりすることで発症する疾患です。インスリンには、血液中のブドウ糖を細胞へ取り込み、エネルギーとして利用させる重要な役割があります。
この働きが低下すると、ブドウ糖が血液中に過剰に残る状態(高血糖)が続き、血管に負担がかかって様々な合併症を引き起こす原因となります。なかには命に関わる深刻な病態に進展することもあります。しかし、多くの場合は症状がほとんどないまま静かに進行するのが特徴です。
健康診断などで血糖値の異常を指摘された場合は、「症状がないから」と放置せず、早めに医療機関を受診することが大切です。
糖尿病内科について
 糖尿病は、現在世界的に増加傾向にある疾患であり、日本でも患者数が年々増え続けています。糖尿病には大きく分けて2つのタイプがあり、1型は膵臓からインスリンがほとんど分泌されなくなるタイプ、2型はインスリンの分泌は保たれていても、その働きが十分に発揮されず、ブドウ糖が細胞内に取り込まれにくくなるタイプです。
糖尿病は、現在世界的に増加傾向にある疾患であり、日本でも患者数が年々増え続けています。糖尿病には大きく分けて2つのタイプがあり、1型は膵臓からインスリンがほとんど分泌されなくなるタイプ、2型はインスリンの分泌は保たれていても、その働きが十分に発揮されず、ブドウ糖が細胞内に取り込まれにくくなるタイプです。
日本における糖尿病患者のうち、大部分が2型糖尿病とされており、初期には自覚症状がほとんどないまま進行するのが特徴です。そのため、気が付かないうちに血糖のコントロールが悪化し、糖尿病腎症・糖尿病網膜症・糖尿病神経障害といった3大合併症をはじめ、様々な合併症を引き起こすことがあります。
糖尿病と一口に言っても、進行度や体質、合併症の有無などは患者様ごとに異なるため、画一的な治療は適しません。当院では、患者様1人ひとりの状態に応じた最適な治療プランをご提案し、重篤な合併症の発症、進展を予防するための診療を行っています。
当院は血液検査の即日結果対応
 当院では、糖尿病の検査として、HbA1cや血糖値の即日結果が分かる血液検査に対応しております。
当院では、糖尿病の検査として、HbA1cや血糖値の即日結果が分かる血液検査に対応しております。
結果をその日のうちにご確認いただけるため、来院回数を減らすことができ、患者様のご負担を最小限に抑えられます。
当院の治療法
糖尿病の管理には、以下の3つの要素をバランスよく行うことが重要です。
- 食事療法
- 運動療法
- 薬物療法
当院では、まず患者様の血糖コントロール状況や体調、ライフスタイルなどを総合的に把握し、その方に合った食事内容や摂取のタイミング、生活習慣に取り入れやすい運動方法などをご提案します。
また、内服薬やインスリン、GLP1作動薬などの注射薬についても、症状や体質に応じて適切な薬剤を選択し、効果的な血糖コントロールを目指して治療を進めてまいります。
糖尿病に伴う合併症の評価
糖尿病は発症しても初期には自覚症状がほとんどないため、多くの場合、健康診断で血糖値やHbA1cの異常、あるいは尿検査で糖の排出が確認されたことがきっかけで発見されます。しかし、高血糖の状態が続くと、血管に障害が生じ、さまざまな合併症を発症するリスクが高くなります。
糖尿病の3大合併症
糖尿病が原因で起こる代表的な合併症には、「糖尿病神経障害」「糖尿病網膜症」「糖尿病腎症」の3つがあり、これらは「3大合併症」と呼ばれています。いずれも細い血管(細小血管)に障害が起こることで、徐々に臓器や末梢に深刻な影響を及ぼします。
これらの進行もまた自覚症状が乏しいため、早期発見のためには定期的な検査と経過観察が欠かせません。
| 糖尿病神経障害 | 末梢神経に栄養と酸素を届ける血管の血流が悪化することで、神経に障害が起こる合併症です。 糖尿病合併症のなかでも比較的早期に出現しやすく、手足の痺れや痛みの感覚の鈍化が見られます。さらに進行すると、筋力の低下や萎縮、異常発汗、立ちくらみ、消化機能の低下、自律神経の障害など、多岐にわたる症状が出現します。 一般的には発症から数年以内に見られることは少なく、時間の経過とともにリスクが高まっていきます。 |
|---|---|
| 糖尿病網膜症 | 網膜には視覚を担う細胞や神経が密集しており、その働きを支えるために毛細血管も集中しています。糖尿病網膜症は、これらの毛細血管が高血糖により障害を受け、眼底出血や網膜のむくみ(浮腫)を引き起こす疾患です。進行すると視野が狭まり、最終的には失明に至ることもあります。日本では失明原因の上位を占めており、早期発見のためには定期的に眼底検査を受けることが重要です。 |
| 糖尿病腎症 | 腎臓は体内の老廃物をろ過して尿を作る臓器であり、その機能には大量の毛細血管が関与しています。糖尿病腎症は、これらの血管が高血糖により損傷を受け、ろ過能力が徐々に低下していく疾患です。 初期には無症状ですが、進行に伴い尿中に蛋白が出るようになり、さらに悪化すると腎不全へと移行し、人工透析が必要になることもあります。実際、日本の透析導入原因の第1位となっています。尿検査や血液検査による定期的な腎機能の評価が不可欠です。 |
その他の合併症
糖尿病が進行すると、動脈硬化の影響で脳卒中(脳梗塞・脳出血)や心筋梗塞、下肢の動脈が詰まる閉塞性動脈硬化症など、重篤な大血管疾患を発症するリスクも高まります。また、感染症にもかかりやすくなったり、傷が治りにくくなる傾向があります。
当院では、これらの合併症の早期発見と評価のために、以下のような検査を実施しています。
- 頸動脈超音波検査
(動脈硬化の進行度の確認) - 腹部超音波検査
(脂肪肝や膵臓、腎臓の評価) - 心電図検査、ホルター(24時間)心電図検査(心臓疾患のスクリーニング)
- 血管年齢測定(CAVI)による血管の硬さの評価やABI検査(足の動脈硬化のスクリーニング)
- 血液検査や尿検査
これらの検査を通じて、糖尿病の進行度や合併症の有無を的確に把握し、必要な治療へと繋げていきます。
糖尿病の治療
 1型糖尿病では、インスリン注射が治療の中心となり、他に選択肢はほとんどありません。一方で、2型糖尿病はその発症背景や症状の現れ方が人によって大きく異なるため、治療内容も非常に多様です。患者様の体調や生活習慣、ご希望を丁寧に伺いながら、個別に治療方針を決定することが重要です。
1型糖尿病では、インスリン注射が治療の中心となり、他に選択肢はほとんどありません。一方で、2型糖尿病はその発症背景や症状の現れ方が人によって大きく異なるため、治療内容も非常に多様です。患者様の体調や生活習慣、ご希望を丁寧に伺いながら、個別に治療方針を決定することが重要です。
2型糖尿病の治療では、特に、生活習慣の改善が重要です。食事療法や運動療法の継続は容易ではなく、多くの患者様が日々努力されています。当院では、続けやすさを重視した治療プランの提案を心がけており、無理なく続けられる方法を一緒に考えてまいります。
薬物療法が必要な場合には、血糖コントロールの状態、年齢、日常の活動量などを総合的に評価し、最適な薬剤を選択して処方いたします。なお、2型糖尿病であっても進行具合によってはインスリン治療が必要となることがあり、その場合も適切に判断・対応いたします。
また、糖尿病は高血圧や脂質異常症といった生活習慣病を併発しやすいため、これらも含めて総合的に診療を行っています。
糖尿病療養指導
当院では、経験豊かなスタッフによる「糖尿病療養指導」を実施しています。
日常生活の不安や悩み、血糖自己測定やインスリン注射の方法など、糖尿病と向き合う上で必要な知識や技術について、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
糖尿病療養指導の内容
- 血糖自己測定のやり方
- ご自身で行うインスリン注射の正しい手順
- 日常生活における注意点
- 低血糖時の対処法
- その他の生活面での疑問・相談対応
糖尿病栄養指導
糖尿病および高血圧・脂質異常症などを伴い、医師が必要と判断した場合には、管理栄養士による「個別栄養指導」を行っています。
管理栄養士が患者様の症状、食習慣、ライフスタイルを丁寧に伺いながら、無理なく取り組める食事改善の方法をご提案いたします。
単なる制限ではなく、「継続できること」を大切にし、日々の暮らしの中で自然に取り入れられる食習慣の見直しをサポートします。
糖尿病は妊娠に関係ある?
(妊娠糖尿病)
 妊娠糖尿病とは、それまで糖尿病と診断されたことがない方が、妊娠中に初めて糖代謝の異常を指摘される状態を指します。
妊娠糖尿病とは、それまで糖尿病と診断されたことがない方が、妊娠中に初めて糖代謝の異常を指摘される状態を指します。
これは妊娠中の検査、特に「糖負荷試験(75gOGTT)」において、以下のいずれか1つ以上の基準を満たした場合に診断されます。
- 空腹時血糖値が92mg/dL以上
- 検査開始から1時間後の血糖値が180mg/dL以上
- 2時間後の血糖値が153mg/dL以上
妊娠糖尿病は初期段階ではほとんど自覚症状がないため、検査による早期発見が重要です。血糖値の高い状態が続くと、胎児が大きくなりやすく(巨大児)、母体にも羊水過多や妊娠高血圧症候群などの合併症を引き起こす可能性が高くなります。
また、出産後に血糖値が正常に戻ったとしても、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが上昇することが知られています。
妊娠糖尿病の発症リスクが高い方には、以下のような特徴があります。
- 尿検査で糖が出た経験がある
- 家族に糖尿病の方がいる
- 過去に妊娠糖尿病と診断されたことがある
- 巨大児(出生体重4,000g以上)の出産経験がある
- 高齢での妊娠
- 双子など多胎妊娠